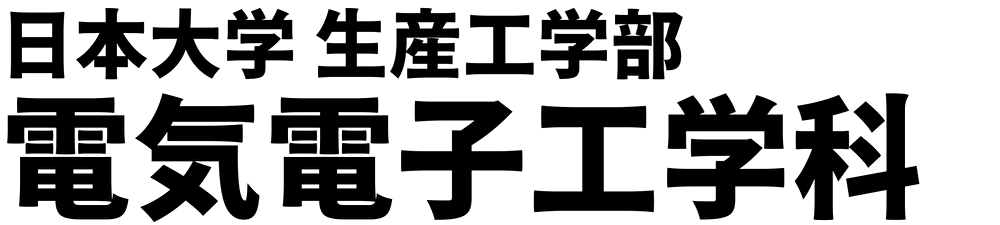#プラズマ理工学
#光計測
#教授

#プラズマ理工学
#光計測
#電気数学Ⅰ
#高電圧プラズマ工学
他
【研究内容】
核融合プラズマに関連した研究として、ヘリコン波プラズマ装置を用いた再結合プラズマの研究を行っています。
核融合炉への熱負荷低減に関連して、プラズマ中の再結合過程等の理解が求められています。
このような高温なプラズマとは対照的に、レーザー冷却技術を用いた極低温プラズマの研究も行っています。
プラズマを絶対零度近くまで冷却することで、プラズマの結晶を生成することが出来ます。
このような極低温プラズマの振る舞いを理解することは、基礎物理への興味と、将来の高度な原子利用へと繋がります。
この他、プラズマ中の物理現象の理解に向けて光渦分光やゴーストイメージング等,様々な計測技術の開発を行っています。
【研究室について】
研究に用いる装置は可能な限り研究室内で設計・製作しています。
学生の間に、ぜひ色々なもの作りに挑戦してください。

#材料物性
#超伝導
#教授
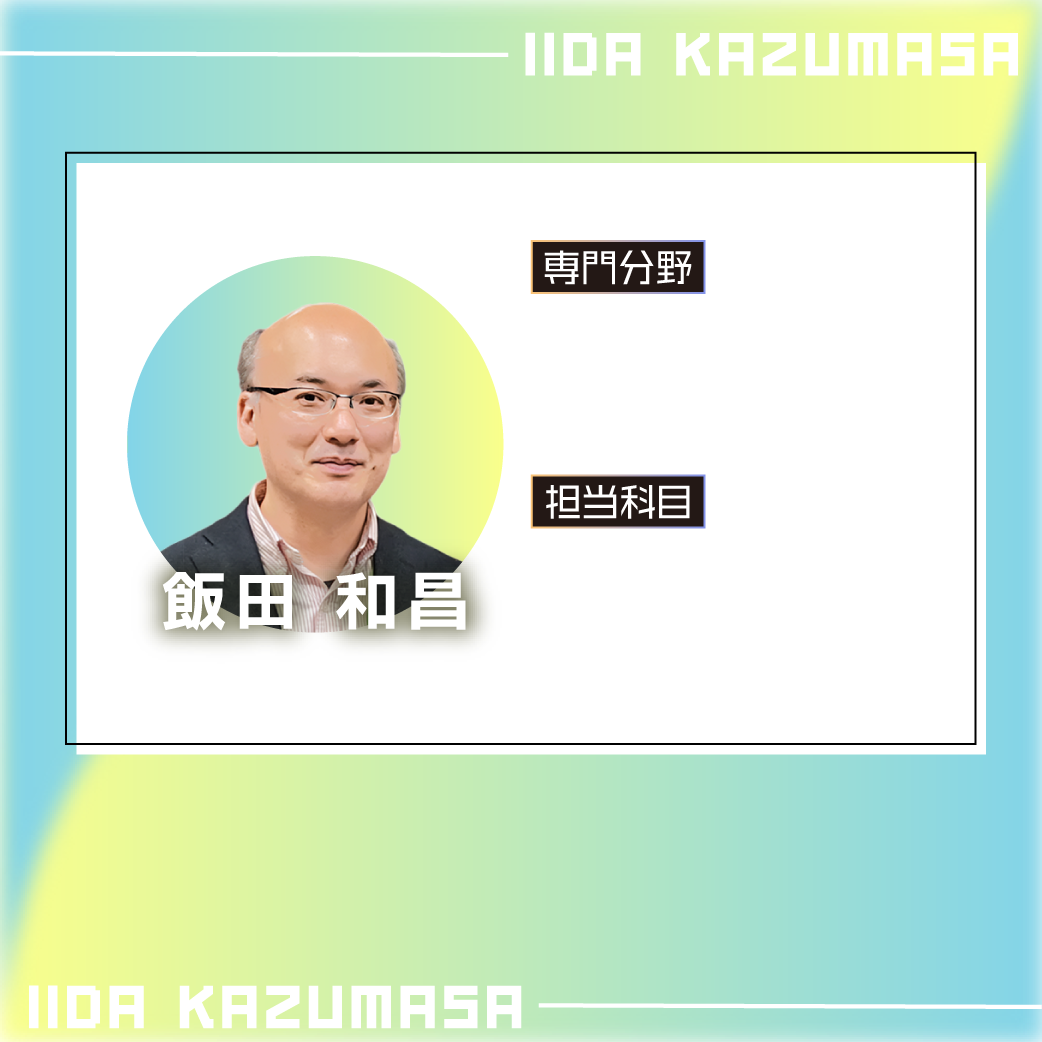
#材料物性
#超伝導
#電気電子材料
#電磁気学Ⅲ
他
【研究内容】
「材料科学」の中心は「材料合成」であるとの信念に基づき、これまでフェライト磁石、磁性ガーネット膜、負熱膨張材料、磁性半導体、トポロジカル物質、磁性半導体、超伝導体など様々な機能性材料の作製に取り組んできました。
ほとんどの材料がある時代に流行した材料のように見えますが、根本は電子が織りなす様々な機能性材料です。
したがって、電子状態を操作する、すなわち物質科学に立脚した材料設計指針を立ててれば、機能を向上させることができます。
現在は、エネルギー材料として有望な超伝導体を主なターゲットとして研究を行っています。
超伝導は電気抵抗がゼロの究極の省エネルギー材料です。
物質科学に立脚した超伝導材料の特性向上を目指した研究を国内外の共同研究者らと推進しています。
【研究室について】
私はイギリス、ドイツと外国で 10 年以上の研究生活を送っている経験から、これからの日本の若手研究者・技術者に対する私の最も大きな願いは国際的に活躍する人材に育ってもらいたいことです。
本学から一人でも多く、そのような人材を育てていきたいと思います。

#光エレクトロニクス
#高速・大容量無線通信
#教授
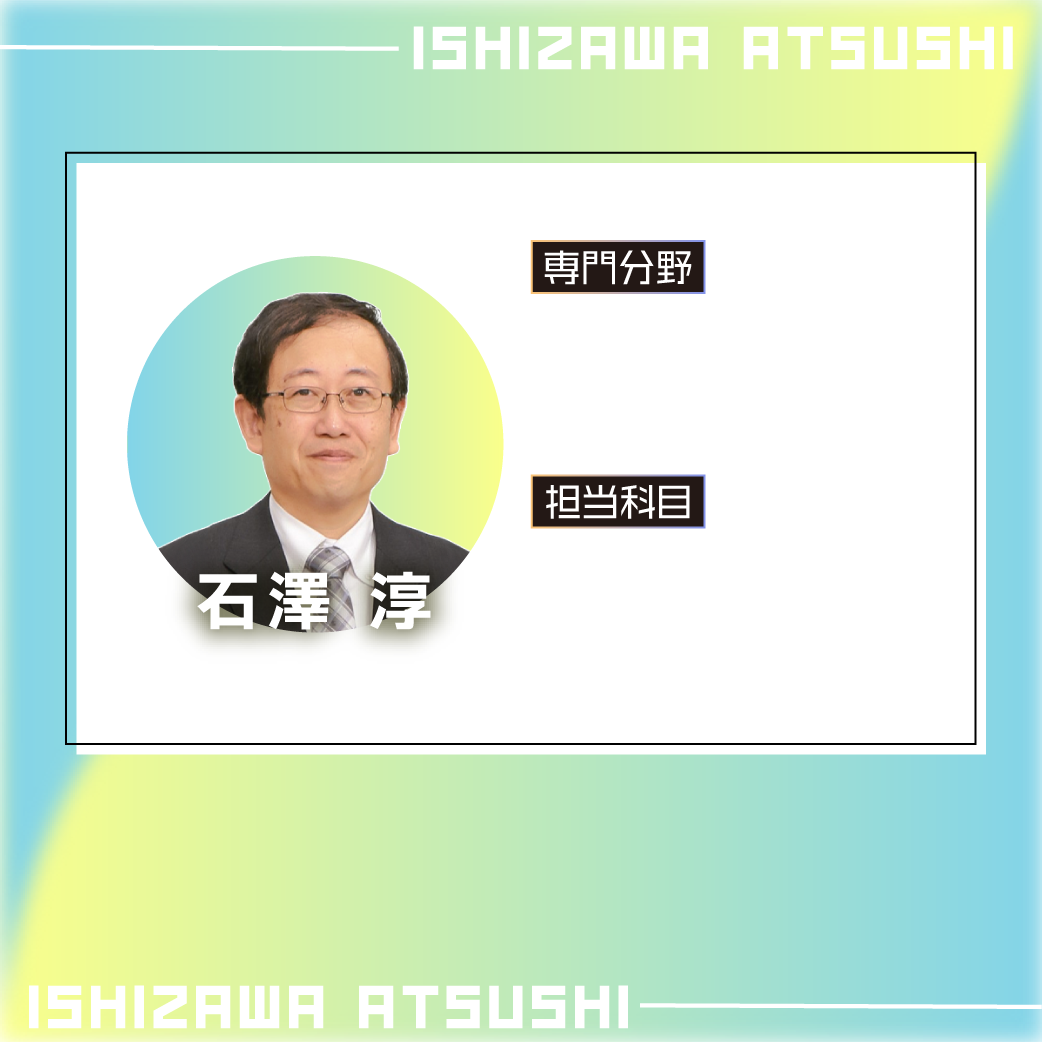
#光エレクトロニクス
#高速・大容量無線通信
#情報通信工学
#伝送路システム
他
【研究内容】
高性能レーザーである「光周波数コム」の光周波数精度を電磁波(テラヘルツ波、ミリ波、マイクロ波)へ転写する技術を用いて、水晶振動子を用いる従来法よりノイズが極めて低い電磁波を発生する方法やその極低ノイズな電磁波を用いた高速・大容量無線通信やレーダー計測の研究を行っています。
これらの研究は、国内外の共同研究者らと協力して推進しており、次世代通信「6G」や航空管制塔における小型飛行物体(ドローンなど)の高感度検出につながる研究です。
【研究室について】
当研究室はNTT物性科学基礎研究所、産業技術総合研究所、
および、カナダ・ケベック大学などと共同研究を行っています。
共同研究先に滞在し、研究討論する機会があり、視野を拡大できます。

#照明設計(視環境設計)
#色彩 #視覚・色覚
#教授
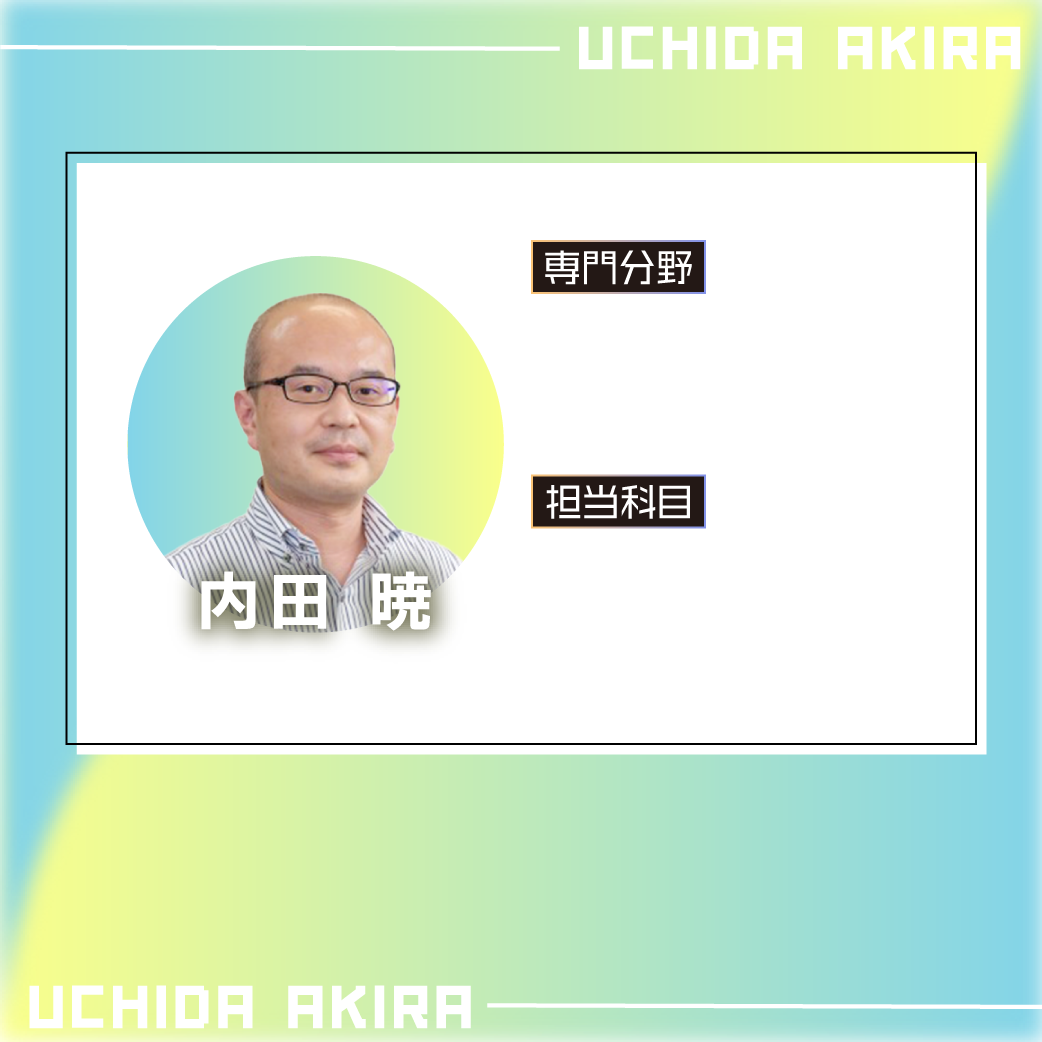
#照明設計(視環境設計)
#色彩
#視覚・色覚
#照明工学
#電気電子工学実験ⅠA・B
他
【研究内容】
人間の生活の質を向上させる照明環境の実現を目指して、主に以下の内容に取り組んでいます。
・LEDや有機ELの効果的な利用方法
・心理物理実験による快適な明るさや色の評価
・シミュレーションによる空間照度の解析と近似的
な推定方法の検討
【研究室について】
暗い場所で「電気をつけて」と言えばその場が明るくなるように、照明は電気・電子に関係するだけではなく、エネルギー応用や情報科学も含めて幅広い分野を網羅します。
また誰もが毎日の生活を幸せに過ごすためにも必要不可欠であるとともに、大いに役立つ研究と言えます。
興味や意欲のある皆さんをお待ちしています。

#静電気応用
#光触媒
#電池 他
#教授
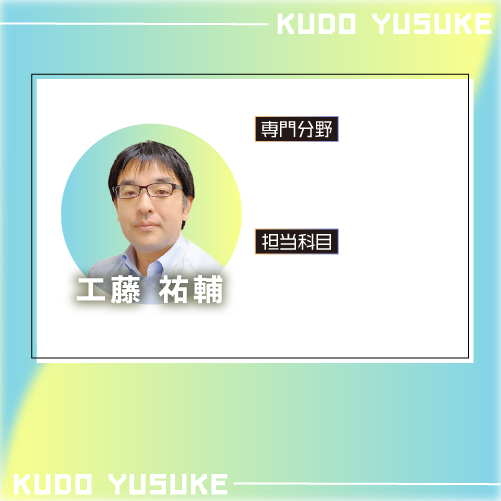
#静電気応用
#光触媒
#電池 他
#電気数学Ⅰ
#電気電子計測Ⅰ,Ⅱ
他
【研究内容】
・静電噴霧による燃料電池電極の作製
液体に高電圧を印加することで発生する霧を利用して,多孔質で表面積の大きい材料の作製が行えます。
工藤研究室ではクリーンエネルギーとして普及の拡大が進められている燃料電池用の多孔質電極の作製し、高性能化を目指して研究しています。
・光触媒の可視光応答化
除菌や防汚などで注目される、光が照射されると有害な物質を分解してくれる光触媒という材料がありますが、安価な光触媒である二酸化チタン(TiO2)はそのままでは紫外線でしか働かず、室内照明で利用される可視光には反応しません。
工藤研究室では二酸化チタンの可視光に反応するよう改良する研究を行っています。
・レドックスフロー電池の開発
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを利用した発電方法は天候の変動が原因となる発電出力の変動が大きいため、今後利用を拡大していくためには大容量の蓄電技術が重要となります。
レドックスフロー電池は充放電を行う事ができる二次電池で、電池容量の大容量化が容易なために注目されています。
工藤研究室では安価な材料を用いたレドックスフロー電池の開発を目指しています。
【研究室について】
工藤研究室では主に研究室で実際に手を動かして実験を行います。
また,大学院に進学してより詳しく研究を行いたい人を歓迎します。

#画像処理
#光応用計測
#ロボティクス
#教授
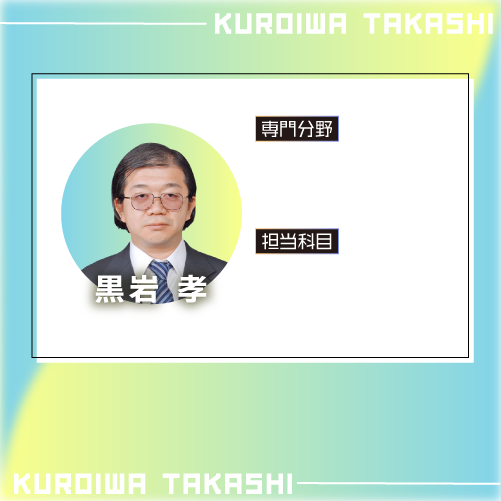
#画像処理
#光応用計測
#ロボティクス
#情報理論
#光通信システム
他
【研究内容】
最近の主な研究テーマと研究内容の概略は以下の通りです。
①動画像処理による走行車両の追跡:交通事故の約半数は交差点内で発生しており、あおり運転など危険な行為も目立ちます。
このテーマではドローンで空撮した動画像を解析し特定の車両を追跡する効果的な方法を研究しています。
②小型ヒューマノイドによる教育支援:コロナ禍でオンデマンドの授業も増えていますが、実験の様な実習教育では対話が必要です。
このテーマでは人間と対話できるロボットを使った教育支援について研究しています。
③3次元レーザ計測によるドローンの検出:ドローンはレーダーでの検知がとても難しく、カメラも搭載しているので盗撮などに悪用される危険性もあります。
このテーマではレーザを用いた3次元計測技術を応用して小型ドローンを検出します。
【研究室について】
大学と高校との大きな違いは、研究活動だと思います。
専門科目の知識も活き、企業が求める問題解決能力も身につきます。
ぜひ研究活動の魅力を知って頂ければと思います。

#非破壊検査工学
#電磁気応用計測
#教授
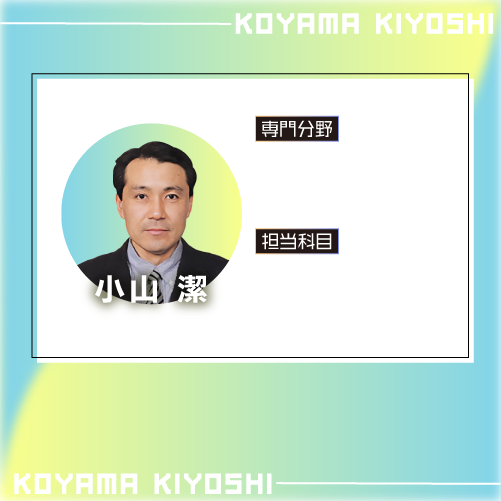
#非破壊検査工学
#電磁気応用計測
#電気数学Ⅰ
#回路理論及び演習Ⅰ
#電子回路Ⅰ,Ⅱ
他
【研究内容】
研究課題テーマは、①構造物などのヘルスモニタリング技術、②炭素繊維複合材に対する非破壊検査技術、③電磁誘導非破壊試験における評価精度向上技術に関する研究などです。
研究領域や分野は、電磁気応用計測、非破壊検査工学になります。
私達の社会生活を便利で豊かに過ごすために、自動車や鉄道、航空機、道路や橋梁、各種プラントなどの社会インフラを安全で安心して長期に亘って使用できることが大切です。
また、それらを構築するために品質の高い工業製品が必要になります。
非破壊検査は、これら工業製品や社会インフラなどの対象物を破壊することなくその状態を検査する技術であり社会生活の維持管理に必要な非常に重要な技術です。
非破壊検査には種々の試験技術があり、中でも電磁気を利用した非破壊試験法である渦電流探傷試験があります。
渦電流探傷試験は、交流電流を流した試験コイルによって導電性の試験体に電磁誘導により渦電流を誘導し、きずなどによって変化を試験コイルの起電力変化を計測し試験対象物の状態を計測する技術です。
【研究室について】
研究に用いる装置は可能な限り研究室内で設計・製作しています。
学生の間に,ぜひ色々なもの作りに挑戦してください。

#半導体電子光物性
#半導体プロセス
#教授
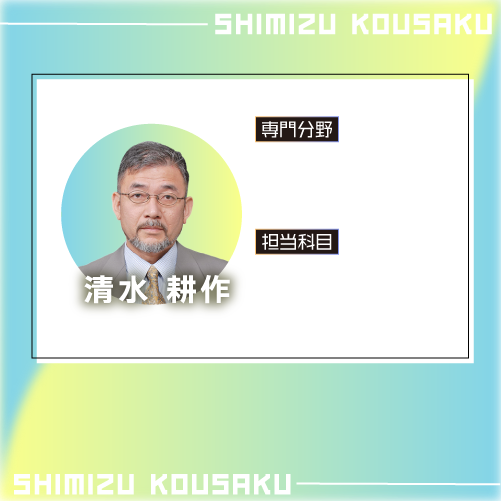
#半導体電子光物性
#半導体プロセス
#半導体デバイス工学
#ナノテクノロジ
他
【研究内容】
① 酸化物や2次元層状物質を用いた薄膜トランジスタの高性能化、高信頼化について検討しています。
近年水素化、酸素化を行うことで、薄膜中の欠陥を低減することができ、高い性能を持ったトランジスタを作製することに成功しています。
現在は、ヘルスモニタリングセンサへの応用を検討しています。
② ヘテロジャンクション太陽電池の高効率化を目指して、亜酸化銅やPEDOT:PSSを用いた太陽電池を作製し、安定化・高効率化に取り組んでいます。
高い変換効率をもつ太陽電池の作製を目指しています。
③我々の身の回りにあるエネルギを有効に利用することでエネルギの無駄遣いを防止し、高い効率のエネルギ循環を目指します。
現在モニタリング装置の開発に取り組んでいます。

#薄膜・表面界面物性
#電気電子材料工学 他
#准教授
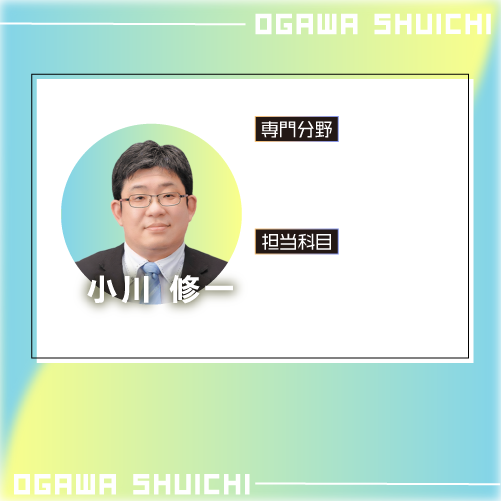
#薄膜・表面界面物性
#電気電子材料工学 他
【研究内容】
① 半導体表面への絶縁膜形成プロセスに関する研究
紫外線光電子分光法による半導体表面のリアルタイム観察を通じて、SiやSiCウェハ上への高品質ゲート絶縁膜形成方法やその成膜プロセスにおける界面欠陥生成メカニズムの解明を目指します。
② 二次元材料物質のデバイス応用に関する研究
グラフェンや六方晶窒化ホウ素などの二次元材料物質をガスセンサや電気分解用電極に応用するため、二次元材料物質への異種原子ドーピング技術の開発やその評価方法の研究を進めます。
③ 炭素系材料の効率的合成方法の開発とそのデバイス応用への研究
ダイヤモンドや非晶質炭素、グラファイトなどの炭素材料を電子デバイスに応用するため、プラズマCVDによる材料合成やその評価方法の開発を進めます。
④ AIを用いた実験・データ解析プロセスの自動化に関する研究
上記の研究を効率的に進めるためには実験やデータ解析の自動化も必要不可欠です。外部の放射光施設や研究開発法人と連携し、AIを活用した実験機器の自動制御や実験データ解析の自動化に関する研究を進めます。

#パワーエレクトロニクス
#自動車工学
#准教授
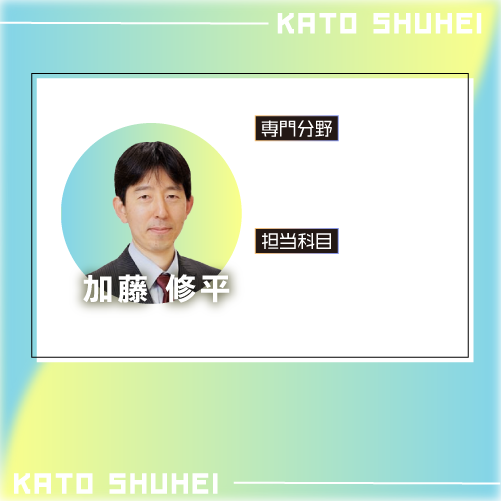
#パワーエレクトロニクス
#自動車工学
#電力発生工学
#プログラミング及び演習
他
【研究内容】
電気自動車の弱点克服の研究
電気自動車(EV)は「走れる距離が短い」、「充電が遅い」が弱点です。
これらの克服として、車両の慣性(勢い)を活用したエコな走行法や高効率な充電回路を研究しています。
太陽光パネルの影対策の研究
太陽光パネルはわずかな影(例えば電柱、落ち葉)が発生すると発電量が著しく低下します。
この対策として,部分影でも可能な限り発電量を維持する回路を研究しています。
水素社会の実現を目指す研究
水素の時代が「来る来る」と言われています。
例えば水素燃料電池自動車(FCV)のブレーキ機構の弱点を克服するモータ制御の研究を行っています。
また,水素エンジン発電機などをきめ細かく運転・停止させ、アイドリングの無駄を省く研究をしています。
【研究室について】
授業で分からない部分は必ず質問してください。
ただ、質問の前にその分からない内容を自分なりに調べ「自分はこう考えているが、それでは理解できないため、どう考えたら良いか教えて欲しい」と学生は必ず自分なりの考えを教員に伝えてください。

#人工知能
#ビックデータ解析
・非線形科学
#准教授

#人工知能
#ビックデータ解析
・非線形科学
#データサイエンス
#電気数学Ⅱ
#電磁気学及び演習Ⅱ
他
【研究内容】
「物理と情報科学の融合で現代科学の難題に挑戦」
人工知能やビックデータ解析は現代社会の基盤技術となりつつあり、これらは科学分野でも大きな流れを生んでいます。
研究室では、核融合プラズマや風力発電・気象・海洋現象・生命科学における複雑な観測データを対象に、人工知能やビックデータ解析の技術を用いた先進的なデータ分析技術の開発を行なっています。
具体的対象は、核融合プラズマの実験データや気象衛星や海洋レーダの観測データ・COVID-19の感染者数推移・脳波・心拍異常の診断等、問題は多岐に渡りますが、これらは「時間・空間に依存する変動」を伴う共通の性質を有しています。
このような観測データは必然的に大規模であり、データから如何に有意な法則を抽出し、予測や物理的理解に繋げていくかは、喫緊の課題となっています。
上記の問題は、個々に大きな研究領域となっていますが、我々はデータ解析や非線形科学の観点から現象を俯瞰的に捉える事で、複雑現象の本質的な理解に基づく予測手法を見出す事を目指しています。
【研究室について】
当研究室は、国内外の研究機関と活発に共同研究を行っており、京大・名古屋大・九大や核融合科学研究所・統計数理研究所、英国ウォリック大学や仏国エクスマルセイユ大学をはじめとした研究機関と緊密に連携しています。
学生の皆さんには、各自の興味に合わせたテーマを設定します。学会発表や学術論文の執筆などを推奨しています。

#テラヘルツ科学
#光物性物理学
#超高速物理学
#准教授

#テラヘルツ科学
#光物性物理学
#超高速物理学
#アンテナ・伝搬工学
他
【研究内容】
本研究室では、フェムト秒レーザーや連続波(CW)レーザーなどの光を用いて、光と物質の相互作用に基づく電気・電子の超高速現象を観測しています。
フェムト秒レーザーを利用することで、10-13 – 10-11秒という極めて短い時間領域の現象をとらえ、物質中の電子の移動や原子の振動を直接観測することが可能です。
また、非線形光学効果や光電流の誘起により、テラヘルツ波(THz波:周波数1011 – 1013 Hzの電磁波)の発生・検出も可能となります。
THz波は物質中の原子や分子全体の振動を観測できる特性を持ち、物性計測や通信への応用が期待されています。
現在は、THz波の発生・検出技術の開発に加え、THz波を用いた電気物性評価、さらに測定結果の多変量解析や機械学習にも取り組んでいます。

#磁性材料
#静電気応用
#専任講師

#磁性材料
#静電気応用
#電磁気学及び演習Ⅰ,Ⅱ
【研究内容】
自動車部品の非結晶材料の高性能化に関する研究
近年は電気自動車技術の発展が目覚ましく、搭載される電子部品の高効率化と高信頼性、小型化、軽量化が求められています。
エンジンルーム付近の高温環境下で使用されることがあることから高温に対応できる材料が望まれています。
電気自動車には様々な電子機器が搭載されていますが、車載機器にはそれぞれ必要な電圧を作り出すために電源回路が組み込まれています。
現在,主流となっている材料であるフェライトはキュリー温度が200℃程度と高温環境では磁気特性が劣化する問題があります。
非結晶合金材料は磁性材料の軟磁性材料で、結晶構造を持たない合金であり、400℃程度で使用した場合にも磁性が失われません。
非結晶合金のノイズ除去性能、損失が少ないことによる高周波用途に注目し、処理方法による特性を検討しています。
【研究室について】
私もこの学部・学科の出身ですので相談や,心配事がなくても話に来てください。
ものづくりや実験を通して楽しんで研究に取り組んでいきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

#光周波数制御
#光高出力化
#助教
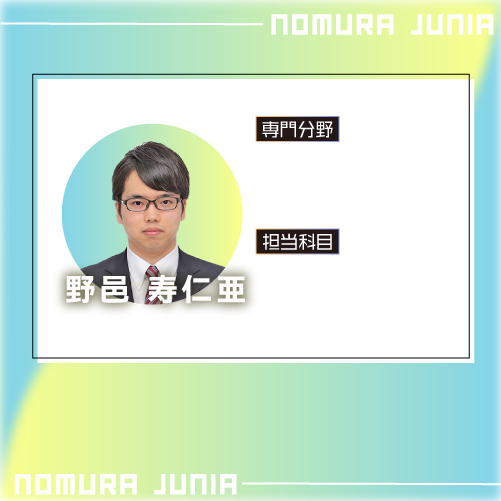
#光周波数制御
#光高出力化
#電磁気学及び演習Ⅰ
#電気電子工学実験ⅡB
【研究内容】
光制御技術と高出力化技術
の融合により、レーザーに”低雑音性”や”高エネルギー”などの高い性能を付与し、ユニークな光源開発を実施します。
さらに上記の光源を適用した通信や計測、医療などの応用開拓を目指します。

#レーザー分光
#波面制御
#助手
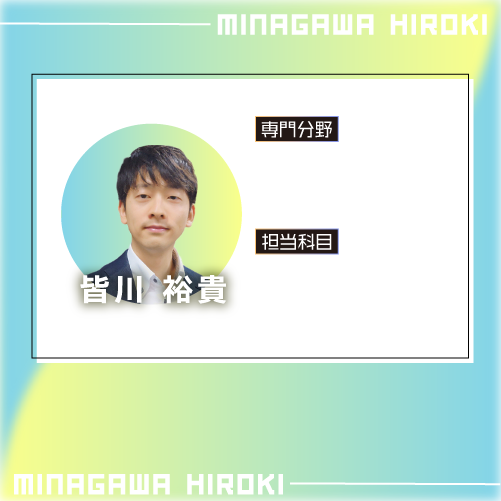
#レーザー分光
#波面制御
電気電子工学実験ⅠA・B
【研究内容】
半導体プロセスや将来のエネルギー源として開発が進められる核融合発電では、極限的なプラズマの制御が求められます。
そのために、先端の波面・偏光制御技術を用いた高度なレーザー分光法の研究を行っています。
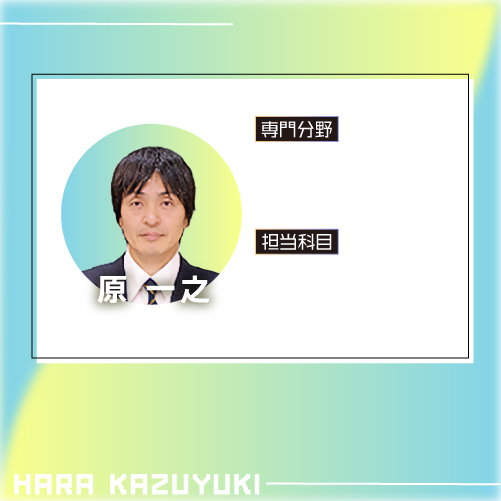
#人工知能の基礎と応用
#ディジタル信号処理
#論理ディジタル回路
#応用情報処理
#特任教授

#加速器科学
#電気電子計測Ⅰ
#電気電子計測Ⅱ
#医用機器工学
#特任教授